時代のメルクマールとしてのファッションデザイナーたちを紡ぐことで、20-21世紀ファッションの歴史をたどります。8月4日(木)から全5回、スパイラル9Fにて。
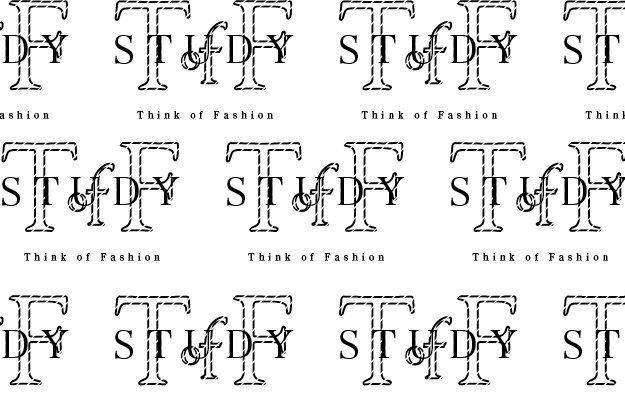
人々の装いについての文化や社会現象を学ぶ
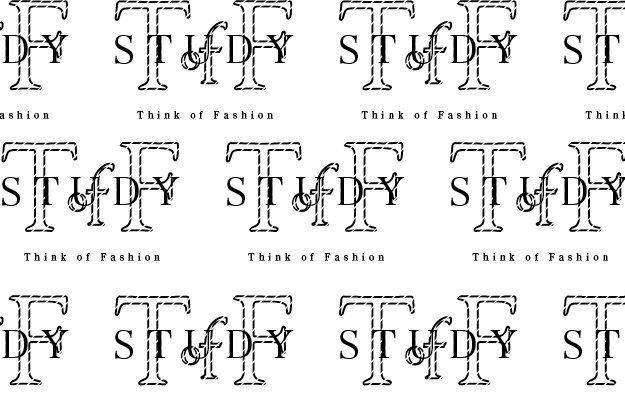
時代のメルクマールとしてのファッションデザイナーたちを紡ぐことで、20-21世紀ファッションの歴史をたどります。8月4日(木)から全5回、スパイラル9Fにて。
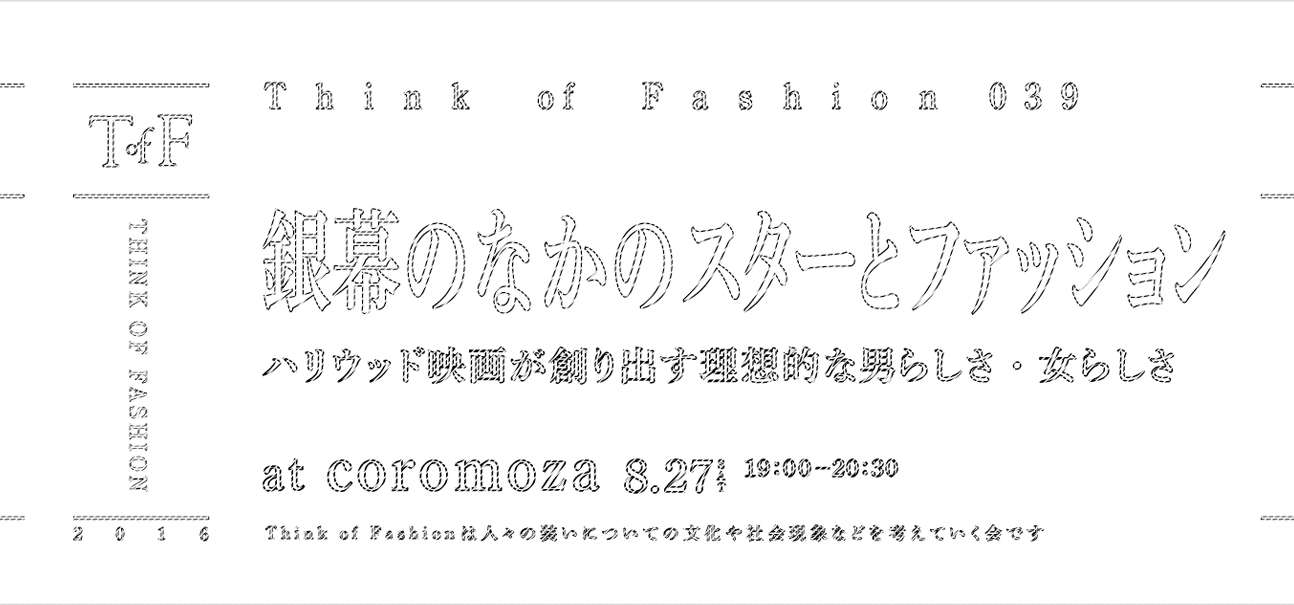
今回は、スターがスター足らしめた時代(1910〜60年代)と「ニュー・シネマ」以降(1960年代後半〜現在)と大きく二つに分け、特筆すべき映画の具体例を交えながらその変遷をみていきます。また、映画のなかの俳優とファッションの関係性、そこに描き出されていた理想の男らしさ・女らしさ、そしてそれらを見る観客の眼差しについて皆さんと考えていきたいと思います。
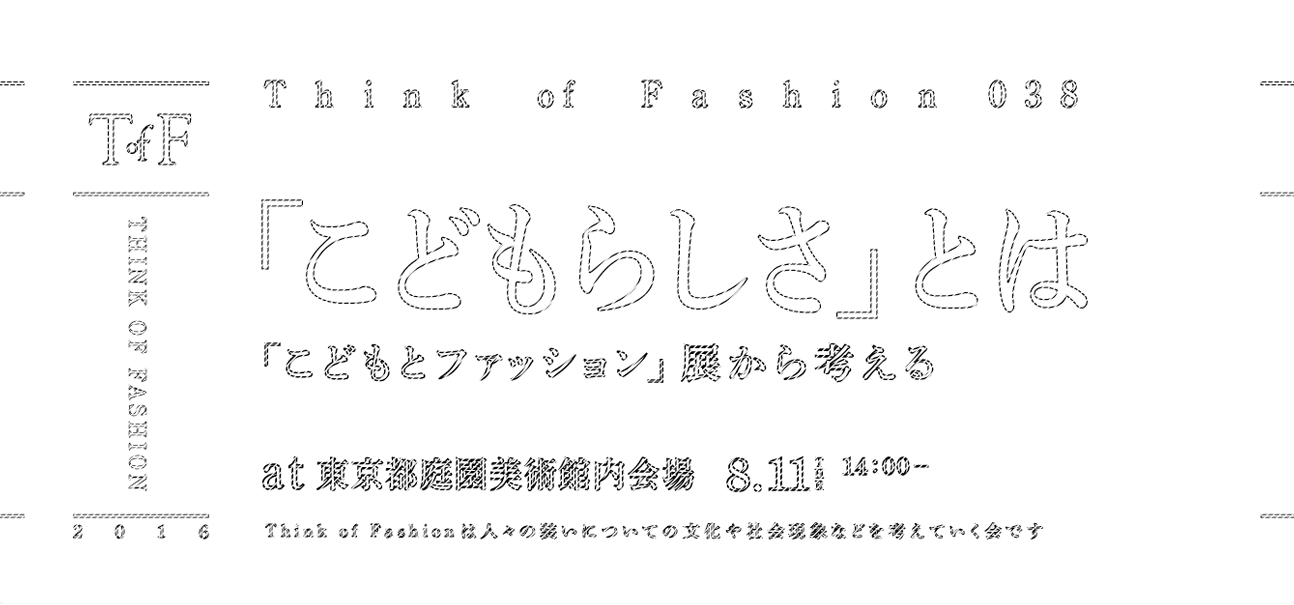
展覧会の『「こどもらしさ」は、こどもが作ったわけじゃない』というコピーが目を引きます。現在、わたしたちが共有しているこども観は、西洋社会では、近代初期から18世紀にかけて定着したとされています。この会では「こどもらしさ」とは誰がつくったのかを、この展覧会を読み解いていくことにより考えていきます。またそのことを読み解く上での衣服が果たす役割も考えていきます。
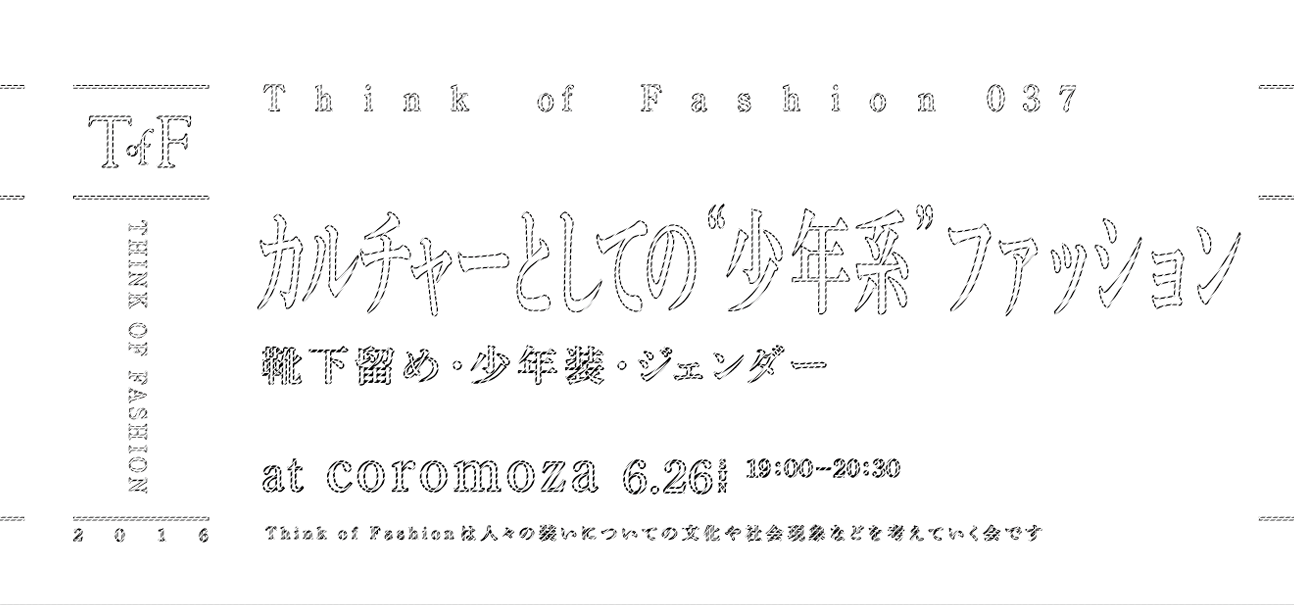
この発表では「靴下留め・少年装・ジェンダー」という3つのキーワードをもとに、服飾史と文化史を横断しつつ少年系ファッションの歴史的な展開を見ていきます。このジャンルを決定付けた映画「1999年の夏休み」以前の状況、そしてtwitter時代以降の傾向とトレンド、刀剣乱舞のへし切長谷部をはじめとする最新動向にも目配りをしつつ、靴下留めの広まりや少年装という用語の成立、雑誌分析を通じて見えるジェンダーも考察します。
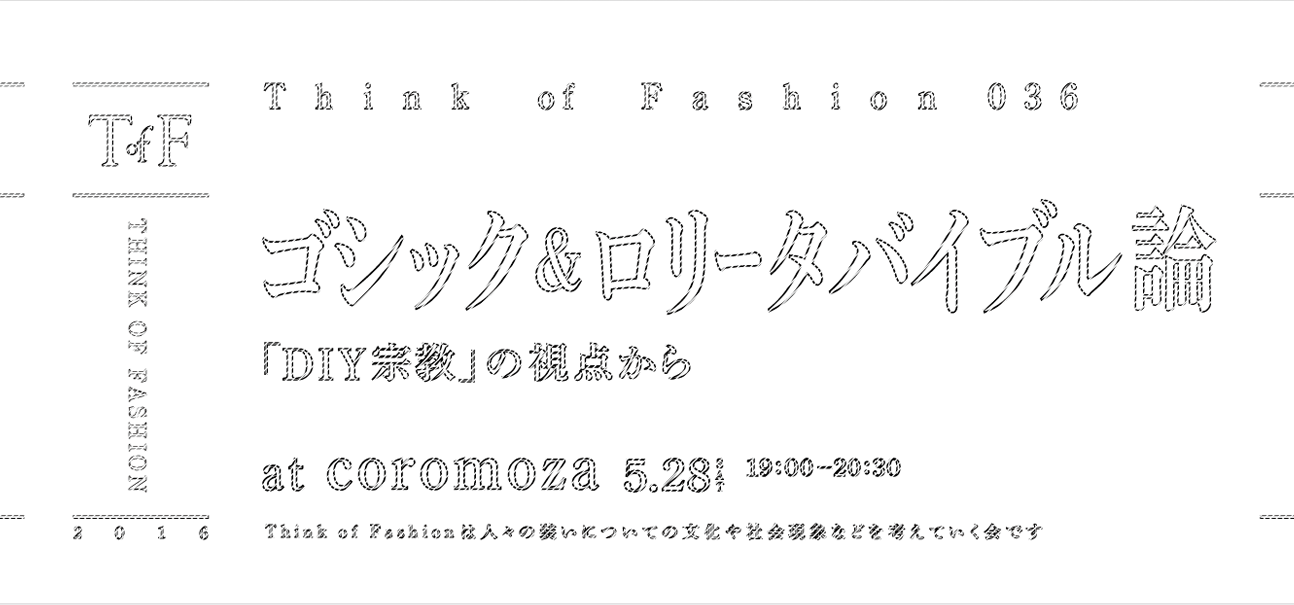
“ゴスロリ”ファッションはいまも人気を博していますが、それには、ムック『ゴシック&ロリータバイブル』が大きく貢献してきました。同誌は、色とりどりの“ゴスロリ”ファッションに、天使/悪魔、星占い、魔女といった「宗教」的なタームを散りばめていることからも、まさに“ゴスロリ”の「バイブル」と言えるでしょう。